‘母’‘子’と言う字
- 母という文字の字源形は
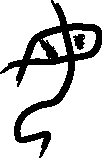 で、これは女を意味する
で、これは女を意味する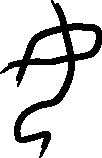 に両乳を示す二点を加えたものです。
に両乳を示す二点を加えたものです。
- 女という文字はひざまずく形と言われていますが、両乳を強調することで母となります。
- 母という文字は{説文解字}では「牧(やしな)うなり」とありますが、これは牧(ぼく)と母(ぼ)で音が似ていることによる仮託で「養う」と同じです。この「養う」から‘補’という言葉と意味的につながっていくかと思います。
- 子という文字の字源形は
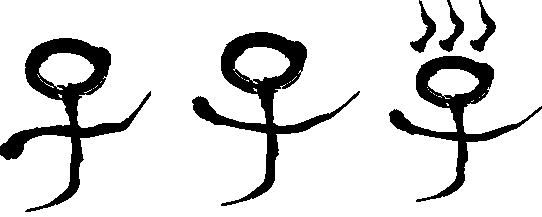 で、幼子の象です。両手を意味する横棒の片側が上下していますが、上部の冠を意味する‘く’形の点も含めて特定の身分を意味し‘字(あざな)’と言う文字へと展開し、この文字が意味を区別する‘字(じ)’へと展義しました。
で、幼子の象です。両手を意味する横棒の片側が上下していますが、上部の冠を意味する‘く’形の点も含めて特定の身分を意味し‘字(あざな)’と言う文字へと展開し、この文字が意味を区別する‘字(じ)’へと展義しました。
- 子は身分を特定するため尊称の意味にもなり、諸子百家の時代には末字に‘子’が付く書物が多く現れました。
- 基本的には王子の称号を意味し、子は次代の世へと現れ出でる養われる存在であって、ここから意味的には‘瀉’とつながる様であり、時間経過の概念も含まれているようです。