-
- 榮衛の榮は、營と言う字もあります。
榮も營もその初字は (エイ:ひあかり)という文字でした。字書にない字ですが、卜文・金文にある庭燎(テイリョウ:にわび。燎はかがりび。たえまなくたくかがりび。ずるずると続いて燃える火)の象形で、たいまつを交叉する形です。 (エイ:ひあかり)という文字でした。字書にない字ですが、卜文・金文にある庭燎(テイリョウ:にわび。燎はかがりび。たえまなくたくかがりび。ずるずると続いて燃える火)の象形で、たいまつを交叉する形です。  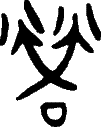
 (えい)という文字がその音として残ります。卜文・金文では氏族の名に用いていました。また、周礼に司 (えい)という文字がその音として残ります。卜文・金文では氏族の名に用いていました。また、周礼に司 氏があって邦の大事のとき、墳燭(麻燭)(燭はともしび。じっとたってもえる灯火)や庭燎を供することを掌(つかさど)ったそうです。 氏があって邦の大事のとき、墳燭(麻燭)(燭はともしび。じっとたってもえる灯火)や庭燎を供することを掌(つかさど)ったそうです。
 に従う字は、みなエイの声義を承(う)けています。 に従う字は、みなエイの声義を承(う)けています。
- と、した上で
- 榮は、
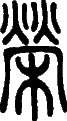 で、たいまつの交叉した形であり、もと火光の華やぐ様をいいました。説文解字に「桐木なり」と梧桐のこととし、次条にも「桐は柴なり」と互訓していますが、栄華・栄誉の義に用いる字で、桐の専名ではなく、桐のうち、華咲きて実らぬ華桐とよばれる種類のものがあって、それを栄桐というそうです。また屋上のつまのそりのあるところを東栄・西栄のようにいって、新死のものの魂よばいの復の礼と言うのを行なうとき、そこから魂が升(昇)降するとしていました。 で、たいまつの交叉した形であり、もと火光の華やぐ様をいいました。説文解字に「桐木なり」と梧桐のこととし、次条にも「桐は柴なり」と互訓していますが、栄華・栄誉の義に用いる字で、桐の専名ではなく、桐のうち、華咲きて実らぬ華桐とよばれる種類のものがあって、それを栄桐というそうです。また屋上のつまのそりのあるところを東栄・西栄のようにいって、新死のものの魂よばいの復の礼と言うのを行なうとき、そこから魂が升(昇)降するとしていました。
營は、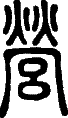 。 。
説文解字に宮に従う字とするのは誤り。
また「営は 居(さふきょ)なり」と解するそうですが、 居(さふきょ)なり」と解するそうですが、 居とは軍営の形式をいうものならいいです。その周辺には庭燎が設けられるので、字はその形。呂は宮の初文の従うところで、相接する宮室の平面形。宮室を造営することを営といって、穴居には営窟といったそうです。[詩、大雅、霊台]に「これを經しこれを營す」とあり、経は測量、営は造営の意。のちすべて計画造作をなすことを営といいました。 居とは軍営の形式をいうものならいいです。その周辺には庭燎が設けられるので、字はその形。呂は宮の初文の従うところで、相接する宮室の平面形。宮室を造営することを営といって、穴居には営窟といったそうです。[詩、大雅、霊台]に「これを經しこれを營す」とあり、経は測量、営は造営の意。のちすべて計画造作をなすことを営といいました。
| この二字の比較から“營”は形に近く造るという意味合いが強く“榮”は質に近く働きと言う意味合いが強いようで、結論として“榮”は滋養する事の作用を言い“營”は滋養作用を作り出すものを示しているといえます。 |
衛は、 。 。
- 説文解字には衞を正字とし、字は韋と
 (イ:めぐる)と行に従うて会意であるとするが、韋は城邑の形である口(い)の上下を巡回する形で、それを行の間においた形声字が衛であると、あります。 (イ:めぐる)と行に従うて会意であるとするが、韋は城邑の形である口(い)の上下を巡回する形で、それを行の間においた形声字が衛であると、あります。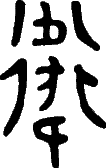
- 卜文・金文の字形に方と言う字に従うものがあって、方は祭梟、首祭りして呪禁とし、防衛する意です。
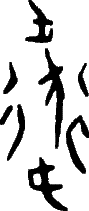
- また、説文解字に「宿衞なり」とするも字の本義でなく、衛とは城邑を守ること。
- 金文に口(い)の四辺に止を加えたものがあり、
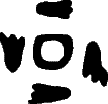 その字が衛の初文。韋・違・衛・圍(囲)はみな韋の声義をとる一系の字です。 その字が衛の初文。韋・違・衛・圍(囲)はみな韋の声義をとる一系の字です。
- 防衛という意味合いは、最初からあったようです。
- では、行とはどんな字かと言いますと、その象形は
   。 。
十字路の形。交叉する大道をいいます。
説文解字に「人の歩趨なり」というのは、字を右歩・左歩を合せて歩行する動作を示すと解したものですが、卜文の字形は十字路の象形。金文に征行・先行・行道・行師のように之往(しおう:ゆく)の意に用います。
十字路は道の交わるところで、そこにはちまたの神がいるとされ、術・衒・衢など、道路で行なわれる呪法の字は、多く行に従う形です。
行とはただ動き回るとは別の、目的やその地点との働きを意味したようです。
- 比較として流は、
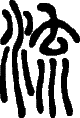 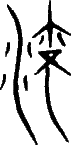 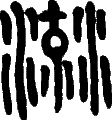 で、正字は で、正字は (とつ)。これは古代には河川の氾濫が多く、その時の流死体を指し、その元の (とつ)。これは古代には河川の氾濫が多く、その時の流死体を指し、その元の (とつ)は (とつ)は もしくは もしくは で、子の生まれ出る形を表しました。 で、子の生まれ出る形を表しました。
|