
表紙>「たこつぼ」句碑を訪ねる旅
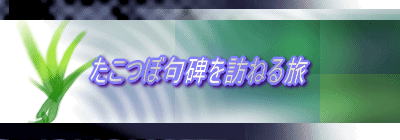 たこつぼや 入れ墨越しに 夏の月 ご存じのとおり、「たこつぼ通信」という名称は芭蕉の句からもらったものです。 −たこつぼや はかなき夢を 夏の月− これがその由来となった芭蕉の句です。 一般には「笈の小文」の旅で芭蕉が明石に泊まった時の作品ということになっていますが、別の作品では明石までは行かずに須磨で詠んだものとなっている。 たこつぼ漁が盛んなのはもちろん明石だから、明石で詠んだのでなければただ頭の中だけで詠んだことになり、それでは興がそがれるので、明石で詠んだことにした、というのが真相のようだ。その程度の粉飾は文学にはつきものだ。 ともあれ、「たこつぼ通信」編集発行人としては、実際にこの句の詠まれた土地で、「たこ」と同じ夢をまさぐる宿願を果たすべく出かけていったのである。 ところが、先述のとおり「たこつぼ」の句はどこで詠まれたのかわかっていない。そこでとりあえず、「たこつぼ」の句碑を探すことにした。事前にインターネットで調べたがその句碑が果たして存在するのかどうか、とうとうわからないまま出発することになってしまった。 たこ焼きのルーツは明石焼きだ 一日目は有馬温泉に泊まり、二日目に須磨寺を参拝し、いよいよ明石へ。 ところが海岸沿いの国道は大渋滞。 そこで、須磨浦駅に車を駐車して電車で明石に向かう。明石駅前で玉子焼き(明石焼き)を食べる。一人前500円。これが「たこやき」のルーツだ。丸い玉子焼きの中にたこが入っている。それが十個板の上に並んで出てくる。それを薄い汁の中にひたして食べる。いわゆる普通のたこやきと違って油っぽくなくあっさりしていておいしい。 そのほかおみやげはさすがに「たこ」関連のものが多い。「たこせんべい」「たこまんじゅう」「たこくんせい」「たこ三昧」。キーホルダーも「蛸のぞき」などというものがあって、蛸の身体の真ん中に穴があいていて、その穴から中をのぞくと明石大橋の風景が見える仕掛けになっている。 思わず買ってしまった。 だじゃれのルーツ 柿本神社 柿本神社というのが例の明石天文科学館のすぐ裏にある。 これは二本の標準時を決める東経135度線上に建っているのだという。 ともかく、その柿本神社だが、人丸山の上にあって、柿本人麻呂をまつっている。 柿本人麻呂はだじゃれになった元祖で、「火止まる」「人生まる」というだじゃれから、火の用心と安産に効験があるという。 それともう一つ、この神社では合格守も有名だ。それは明石のたこの姿をした置物だ。これがなぜ合格お守りなのか。さてこれもだじゃれで考えてくだじゃれ。答えは文章の最後で。 さて、この神社へ上る階段の両側に桜の木があり、そこにおびただしいセミがとまっていた。今年はセミの当たり年のようだ。セミというやつはたまに大発生するときがある。一本の木に最低100匹はいただろう。何しろ10cmに一匹はかならずとまっているのだ。近づいていっても逃げようともしない。手で簡単に捕まえられる。これだけ大発生すると、セミの生命本能、危機管理能力も鈍くなるのかもしれない。 なんと、偶然に句碑発見 明石天文科学館と人丸神社のちょうど真ん中にあたるところに休憩できるスペースがあり、なんとそこに探していた「たこつぼ」の句碑があるではないか。 なんのことはない。こんなところにこんな簡単に見つかるとは思いも寄らなかった。 神社という うまい商売 とにかく暑い日だ。歩いているだけで汗がしたたり落ちてくる。神社のお守り売り場はとざされており、インターホンの横に「ご用の方はこちらを押してください」という張り紙があった。 神社というものは勝手につくっていいものではなかろうが、できてしまえば人が勝手にお賽銭を置いていくのだから全くこんなうまい商売はあるまい。・・と、また例の癖がでてしまう。何とかして働かずに食べていく方法がないものかと、そればかり考えているのだ。 そういうときいつも、「遊びたいとか、休みたいとか、そぎゃんこつ考えるごとなったら、死ね」という武田鉄矢の詞が浮かぶのだ。 しかし同時に、「遊びをせんとや生まれけん、たはぶれせんとや生まれけん」という俗謡も同時に浮かぶのだ。 それにしても、この旅行中、あちこちの公園や高速道路のパーキングでたくさんの乞食におめにかかった。この不景気による失業者だろうか。団体客が捨てていった弁当箱のふたを一つ一つ開けては残り物をビニール袋に詰めこんでいるおじさんを見た。周りの人々はだれもみななるべくそちらを見ないようにしているようだった。 なぜ見てはいけないような気がしてしまうのだろうか。それはやはり神々しさとでもいおうか、我々凡人にはとても到達できないところにいるからだろう。あるいは消費文明という我々が作り上げたシステムへの負い目というものがあるからだろう。われわれの食べ残しを食べることで彼らは我々の「贅沢という罪」を浄化してくれているような気がするのだ。 しかし、考えてみると食べ残しというのは案外清潔なのだ。一度口に入れてからはき出したものなどないのだから。ほとんどが手をつけないでそのまま残したものなのだから。 乞食を卑賤な目で見るのもおそらく部落差別同様に作られた制度なのだと思う。 「働かざるもの食うべからず」というが、働かないで食べている者などくさるほどいる。そもそも株の売買でもうけるなどというのは働くことのうちに入れるべきではない。それなのになぜ乞食だけが肩身の狭い思いをしなければならないのか。 生き物はまず食い物のあるところに住処をつくる。乞食は食い物のたくさんある高速道路のパーキングに集まる。非常に単純明快ではないか。 しかし、考えてみれば衣食住以外の仕事は本来必要ないのだから、あとは全て乞食と変わらないのだ。芸術家と乞食はほとんど同じものだ。俳優は河原乞食とよばれていたのは周知のとおりだ。 やくざという生き方 それでは、やくざという商売はどうだろうか。 二日目の旅館は明石海峡大橋の見える淡路島の「淡海荘」というところだった。 風呂へ入ったときのことだ。 脱衣所のいすに座り扇風機にあたっていた人の背中には鮮やかな色の絵が彫りつけられている。その筋の人であることは一目瞭然であった。一瞬ひるんだが、こういう人はけっこう礼儀正しいものだと思い直し、余計な刺激を与えないようにして、何でもないふうに早く湯に入ろうと思って浴室のドアをあけてみてびびった。 そこはさきほどの方と同業の方々で占められていた。 みなさん赤青黒の絵を体中に彫りつけていらっしゃる。 体格もたいへん立派で千代大海のような方もまじっていらっしゃいます。 かわいい男の子と女の子もいて、お父さんが頭を洗ってさしあげている。 一人だけ絵のない人がいたので、「よかった。仲間だ」と思ったら、「おい、石けんとってくれ」とかいって親しそうに話をなさっていたので、その方もやはり同業者でいらっしゃることがわかった。 こういうときはやはりいつもと変わらず、というよりもむしろいつもよりゆっくりと身体を洗ってね、さりげなく速やかに出ましょう。てなわけで、脱衣所に向かって、気持ちはゆっくりだが、身体はかなりあせっていたようでこけそうになって上がった。 すると、先ほど子どもの頭を洗っていたお父さんが私を追いかけるようにして上がっていらして、まずはイスにでんと腰掛けて一服しはじめた。そこへかわいい女の子が続いて上がってきた。 そのとき、「ぶおおーー」というどえらい音がした。 そのお父さんがでかいおならをこいたのだ。 しばしの沈黙の後、女の子が「くさーい」と言った。 「そうか、くせえか、ぐわははは」と言って、その筋のお父さんは笑った。 一瞬にして呪縛が解け、私も思わず笑いそうになったが、何とかこらえて顔をそむけたまま急いで着替えてた。後ろ姿はあきらかに焦りを表していただろう。 いそいでその場から立ち去ろうとしたのだが、浴室にせっけんを忘れてきたことに気づいた。 着替えてしまったので仕方なく、服を着たまま浴室に入ろうとすると、ちょうど入り口付近で、出ようとしていた「その筋の人」とぶつかりそうになってしまった。 「やばい」と思った瞬間、その筋の人から、 「あ、すいません」という言葉が出た。 「いえいえ」とか言いながら私は石けんをとってきたのである。 もしかして、この人達は、その筋の人ではなく、ただの「入れ墨愛好会」か何かかもしれないぞ、などと急に気が大きくなったりもしたのである。 でも、やっぱり人前であのような豪快な屁をこけるのは「その筋の人」に違いない。 それにしてもあの方達はどんな仕事をしているのだろうか。働くとはどういうことなのか、謎は深まるばかりの今回の旅であった。 芭蕉の職業は俳諧の宗匠である。 旅をしながらその行く先々で句を詠み、弟子と句会を催し、弟子にめんどうをみてもらっている。 それはほとんど乞食といってもいい。 おそらく芭蕉自身には自らを乞食ととらえる意識はあったはずだ。例えば次の句 −猿を聞く人捨て子に秋の風いかに −野ざらしを心に風のしむ身かな 合格守の答え タコ=オクトパス=置くとパス(置くと試験に合格するというだじゃれ) |